2022年3月、60歳で会社を定年退職しました。
年金受給は65歳からと考えています。
でも国民年金、未納期間があるために満額はもらえません。
会社に入ってから定年退職するまで、つまり60歳まではきっちりと納付しています。
ただ、20歳から会社に入るまでの学生の期間が未納期間となっていました。
学生の頃は国民年金を納付するという意識は、正直まったくなかったです。
ただでさえ多くない国民年金。
なんとかならないものか。
いろいろ調べると、未納期間の部分を後から払うことができる「任意加入」という制度がありました。
任意加入の条件はいくつかあって、また、払い方もいくつかあるようです。
本を読んでも、ネットで調べても、年金事務所に電話しても、いまひとつ腑に落ちません。
定年退職した後、直接年金事務所に行き、いろいろ教えてもらいながら任意加入の手続きをやってきました。
保険料納付の方法、自分にとって、どの方法が一番お得なのかを教えてもらい、手続きしてきました。
未納期間40ヶ月の任意加入手続き
年金事務所に行って手続きを行ったのは4月20日でした。
そして、僕の未納期間は40ヶ月ありました。
納付方法はクレジットカードにして、「とにかく一番お得に納付する方法を教えてほしい」とお願いしました。
定年退職前の2〜3ヶ月前に調べた時、前納すると割引があるけれど、クレジットカードだと2月までに手続きしないといけないことがわかっていました。
なので、「今できる方法で一番得なのは何か」は、聞くしかないと思ったのでした。
担当の方は「わかりました。別の者とも相談して見つけてきます」と快く引き受けてくれました。
結構な時間が経って「一番お得な方法を見つけてきました」と教えてくれたのが、これです。
- 最初の12ヶ月分は、現金一括振込をする。
- 次の2年分は、クレジットカード一括払いをする。
- 残りの4ヶ月分も、クレジットカード一括払いをする。
この方法だと、全てに一括払いの割引が効いて、この「4月時点・クレジットカード払い」では一番お得になるとのことでした。
手続きを終えると、上記2と3の前には支払いの案内が送付されてくるようです。
ということで、その場でいくつかの書類を記入して、任意加入の手続きとクレジットカードの登録手続きを完了しました。
国民年金を調べよう
僕が国民年金について調べ始めたのは、2021年度になってから、つまり定年退職まで後1年となった頃からです。
それまでは「ねんきん定期便」が届いた時に、
「年金、こんなに少ないんや・・・」
「国民年金、満額でないのは学生時代の未納があるからか・・・」
と気落ちしながら、仕方ないことだと諦めてました。
定年退職後の、老後のお金のことを真剣に考え出して、「年金」についても本などで調べました。
- 『定年前後のお金と手続き』横山光昭 扶桑社
- 『定年前後の手続きガイド』中島典子 長尾義弘 宝島社
- 『定年後のトクする働き方・仕事の探し方』日本実業出版社
主に読んだのはこの3冊です。
内容的には重なっている部分も多いですが、いろんな気付きがありとても参考になりました。
とりわけ「国民年金を今から増やすことができる!」と気づかせてくれたのは大きかったです。
さらに、未納期間を任意加入で満額にするだけでなく、付加保険料を追加することで年金額をUPさせる方法があることも知りました。
参考までに、上記3冊についての簡単な感想を記しておきます。
ちなみに毎年改訂版が出されているようです。
『定年前後のお金と手続き』横山光昭 扶桑社
定年前後の生活に関わる全般について、一通りの事柄が載っています。
少し前に話題となった「老後2000万円問題」も含めて、お金について知っておいたほうがいいこと、老後の住まい、介護、相続についても書かれています。
「知っておきたいことが何か」はだいたい網羅されているので、あとは必要に応じて、自分で深掘りしていけばいいかという感じです。
『定年前後の手続きガイド』中島典子 長尾義弘 宝島社
定年退職の5年前から、そして定年退職してから65歳までの間に、どんなことがあるかをスケジュール形式で示してくれています。
なので、今何をやらないといけないか、次何を考えないといけないか、が確認しやすいです。
退職によってかかるお金や、今年改正された年金制度のことも割と詳しく載っています。
「任意加入」と「付加保険料」については、この本で知りました。
『定年後のトクする働き方・仕事の探し方』日本実業出版社
定年退職後に働く場合、どんな働き方があるのか、がメインな感じです。
具体的例を示して書かれているので、こんな働き方もあるんだと知り、ちょっと目から鱗の感じがしました。
「もらえるお金」「払うお金」についてもちゃんと載っています。
年金を増やすための「任意加入」「付加保険料」についても書かれています。
国民年金について新たに知ったこと
今回、任意加入の手続きを行って、今更ながら知り得たことです。
未納期間
国民年金を納付するは、20歳以上60歳未満の期間です。
僕の場合、1961年12月生まれなので、1981年12月から2021年11月までの480ヶ月となります。
ここで僕がちゃんと理解できていなかったことがあります。
- 会社からの給与では、「国民年金保険料」ではなく「厚生年金保険料」が引かれている。
- 60歳になっても、それ以前と同額の「厚生年金保険料」が引かれている。
- なので60歳以降も、「厚生年金保険料」を払っている間は「国民年金保険料」も払っている。
と勘違いしていたのです。
つまり、2021年12月から2022年3月までの間、厚生年金保険料を払うと国民年金保険料も払ったことになる、と思っていたのです。
今回、未納期間が40ヶ月あるとわかって理解しました。
国民年金保険料の納付期間は、60歳になる前月で終了し、それ以降に厚生年金保険料を納付しても国民年金の加入期間は増えないということです。
ただし、厚生年金保険料は支払っているので、年金額自体はその分増えるようです。
(帰ってから調べたけど、詳しい仕組みは難しくてよくわかりませんでした。)
任意加入と付加保険料
未納期間があると国民年金が満額になりません。
これを満額に近づけるための制度として、未納期間の保険料を納付する任意加入があります。
任意加入の条件はいくつかありますが、主だったものは以下の条件です。
- 60歳以上65歳未満
- 老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていない
- 厚生年金保険に加入していない
僕の場合、任意加入で納付する保険料の合計と年金が増える額を計算すると、だいたい10年ちょいでとんとんとなります。
年金をもらい始めて10年を超えるくらい生きれば、得するということです。
また、任意加入と併せて付加保険料を納付すると、さらに年金額を増やすことができます。
1ヶ月につき400円を付加保険料として追加納付すると、「付加保険料納付月数 × 200円」の額が年金の年額に加算されるのです。
納付する付加保険料の合計と年金が増える額は、2年で同じ金額となります。
つまり年金をもらい始めて2年より長く生きると、得をするということです。
僕自身の考えですが、少しでも年金額が増えるなら「任意加入」と「付加保険料」はやることを検討していいかなと思います。
人生100年と言われる時代です。
長生きに備えて、少しでも多く年金をもらいたいですよね。
国民年金の保険料納付方法
日本年金機構のホームページを見ると、国民年金保険料の納付方法がでています。
納付方法は「現金」「口座振替」「クレジットカード」の3種類。
前納制度があり「6ヶ月前納」「1年前納」「2年前納」での前納割引がある。
また、割引額は「口座振替」が一番高い割引額で、「現金」と「クレジットカード」は同額。
前納制度を利用する場合「口座振替」「クレジットカード」は2月末までが申込み期限。
「現金」だと2月1日から受け付けているが、2年前納だと4月末までに支払う必要がある。
今回、僕はクレジットカードを選択しましたが、一番お得なのは口座振込です。
クレジットカードにしたのは、2つの理由からです。
- 通帳(カード)と銀行印を持って行ってなかった。
- クレジットカードだとポイントがつくだろう。
窓口で口座振替のほうがお得ですよと言われましたが、ややこしい手続きは対面で聞きながらやるほうがいいと判断し、クレジットカードにしたのです。
(ただ、調べてわかったのですが、ポイントが付く付かない、ポイントの付与率はカードによって全然違っています。自分のカードはどうか、ちゃんと確認する必要はあります)
実際、また出直してくるのも大変だし、家で書類を記入するのも面倒です。
それに後で変更することもできるようなので、とりあえず一旦終了にしたかったのが本音です。
納付方法とか割引額とかは、これからも変更があるんじゃないかと思います。
自分が行う時に、最新情報を確認してその時に一番お得な方法を選択されることをおすすめします。
まとめ
会社を定年退職後、年金がいくらもらえるのか。
これは今後生きていく中で、とても重要な問題です。
とりわけ国民年金の額は、働いている間に納付してきた期間で決まるため、60歳を超えると確定してしまいます。
でも、未納期間がある場合、もしかしたらまだ増やせる可能性があります。
年金事務所、正直行く前はちょっとどんな感じなのかなあと思っていました。
でも、担当の方は、親身に聞いてくれて親切に考えてくれました。
これは僕が行ったとこ(川越)だけでなく、おそらく他の事務所も同じなんじゃないかと思います。
親身に聞いてくれて、ちゃんと解決しようとしてくれたと感じました。
第一歩として、本やネットで調べること、年金についての知識が深まってくるので大事なことです。
その次には、一度は年金事務所に行って、直接いろいろ確認しましょう。
そして、自分にとって納得できる最善の方法をみつけましょう。
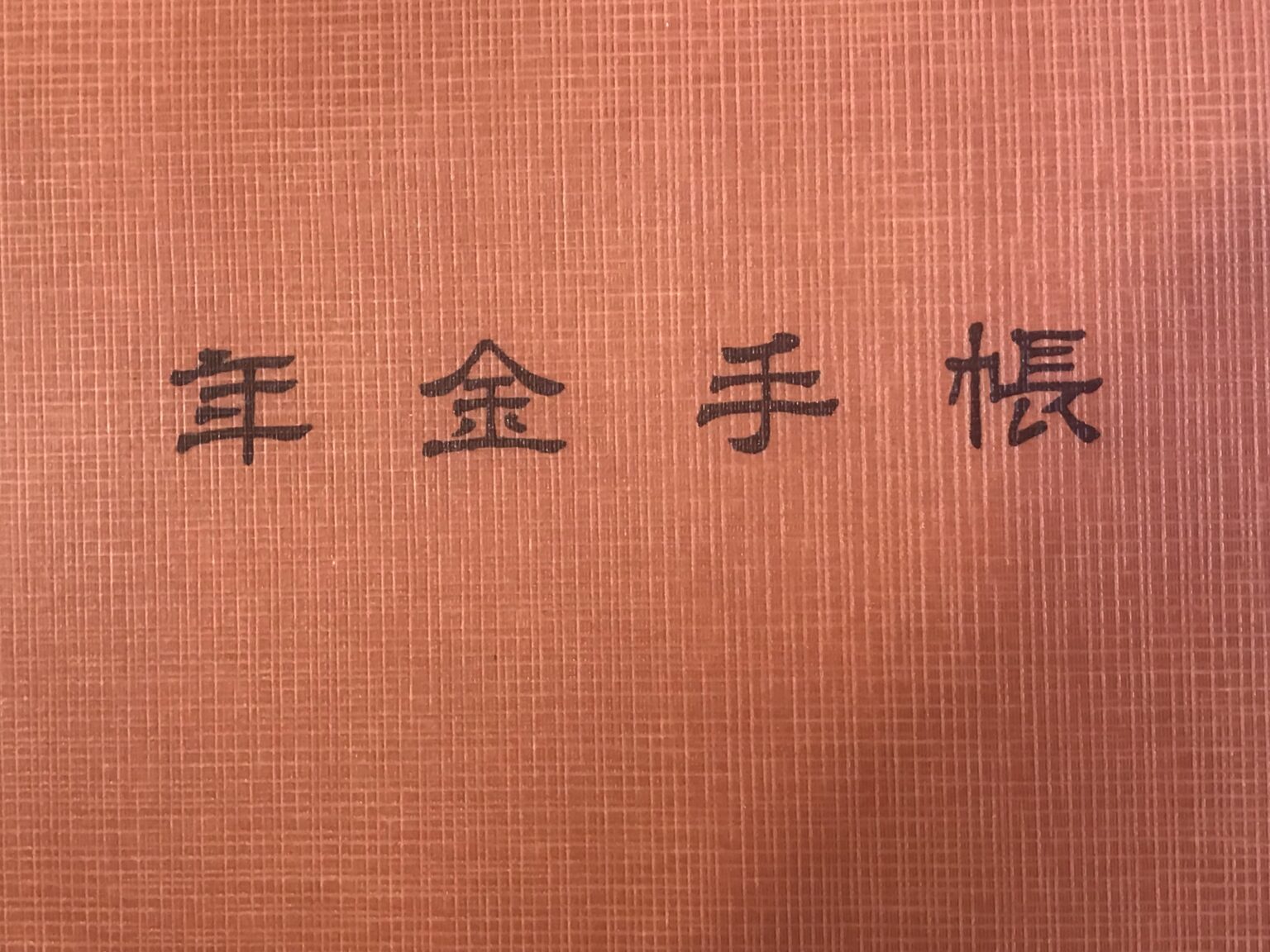

コメント